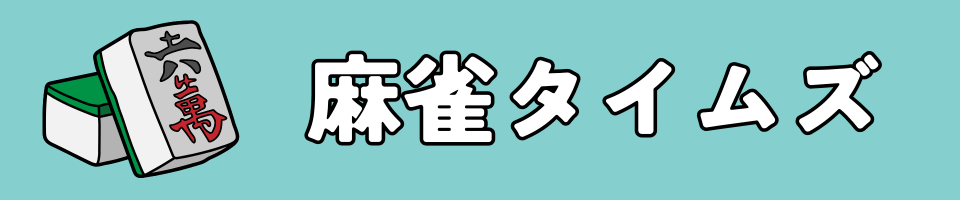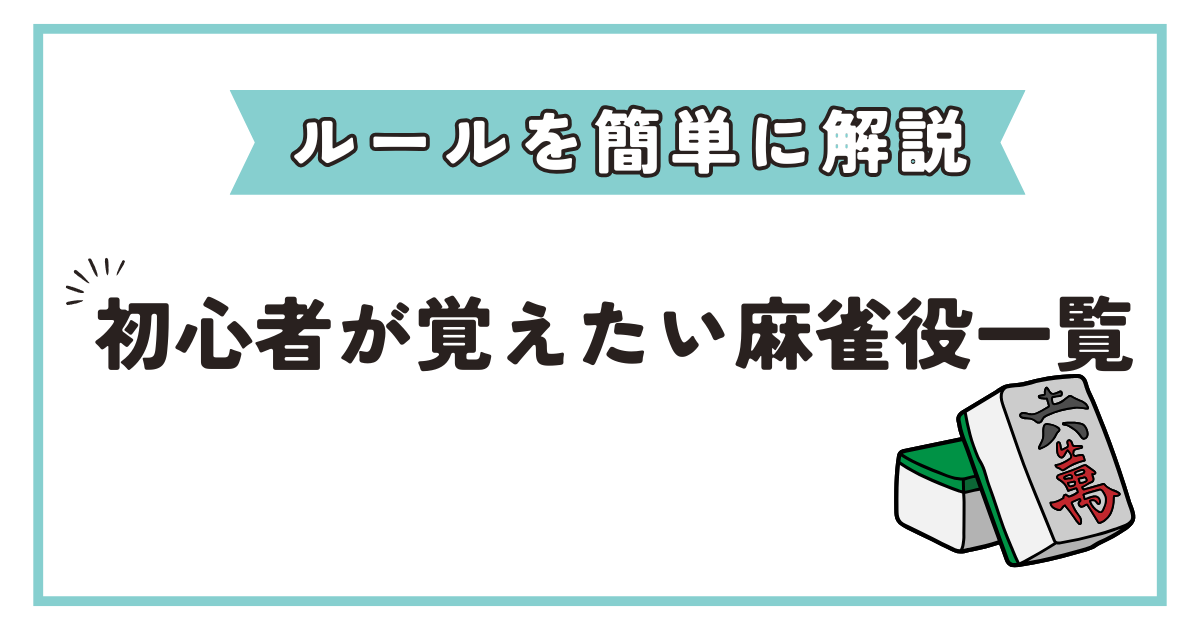麻雀を始めたいけれど、「ルールが難しい」と感じていませんか?
初心者の多くが、役の作り方や点数計算に戸惑い、「意味不明」と思うこともあるでしょう。
しかし、基本ルールを押さえれば、誰でもスムーズにプレイできるようになります。
この記事では、麻雀の基本ルールをわかりやすく解説します。
また、麻雀の役を紹介し、初心者がまず覚えるべきポイントをまとめました。
麻雀初心者講座として、ゲームの流れや点数計算の基本、やってはいけない行動なども解説します。
さらに、初心者向けのゲームアプリを活用した練習方法についても紹介するので、実践的に学びたい方にもおすすめです。
麻雀の基礎をしっかり理解し、楽しくプレイできるようになりましょう。
【記事のポイント】
- 麻雀の基本ルールとゲームの流れ
- 初心者でも覚えやすい役や点数計算の基本
- やってはいけない行動や注意点
- 初心者向けのゲームアプリを活用した練習方法
麻雀のルールを簡単に理解しよう

麻雀初心者講座:基本ルール
麻雀は、4人で対戦する戦略性の高いゲームです。牌を組み合わせて「役」を作り、最初にアガった人が得点を獲得します。しかし、初心者にとってはルールが複雑に感じられるかもしれません。ここでは、麻雀の基本ルールをわかりやすく解説します。
プレイヤーの人数とゲームの目的
麻雀は基本的に4人でプレイします(3人で遊ぶルールもありますが、ここでは一般的な4人麻雀を解説します)。各プレイヤーは、手持ちの牌を組み合わせてアガリを目指します。最終的に得点が最も高いプレイヤーが勝者となります。
牌の種類と使用枚数
麻雀では、全部で136枚の牌を使用します。これらの牌は「数牌」「字牌」「赤牌」に分類されます。
・数牌(シューパイ):萬子(マンズ)、筒子(ピンズ)、索子(ソーズ)の3種類があり、それぞれ1~9の数字が描かれています。
・字牌(ジハイ):東、南、西、北の「風牌(フォンパイ)」と、白、發、中の「三元牌(サンゲンパイ)」があります。
・赤牌(アカハイ):通常の牌に赤色がついたもので、得点が上がるボーナス牌として扱われます。
アガリの形と役の基本
麻雀で勝つためには、決められた「アガリの形」を作る必要があります。一般的には「4面子1雀頭」という形になります。
・面子(メンツ):3枚1組の牌のセットで、「順子(シュンツ)」または「刻子(コーツ)」で構成されます。
・雀頭(ジャントウ):2枚1組の同じ牌をそろえたもの。これがないとアガリとはなりません。
また、アガるためには「役」が必要です。役は、特定の牌の組み合わせやプレイスタイルによって成立します。
ゲームの流れ
麻雀の基本的な流れは以下の通りです。
- 親と子を決める:最初の親(親番)をサイコロで決定し、残りの3人が子になります。親は点数のやりとりで有利な立場にあります。
- 配牌(ハイパイ):各プレイヤーに13枚の牌が配られます。親は最初に1枚ツモ(牌を引く)して14枚でスタートします。
- ゲーム進行:親から順番に、山から1枚ツモして不要な牌を1枚捨てる。この流れを繰り返し、役を作る。
- アガリの宣言:アガリの形が完成したら「ロン」または「ツモ」と宣言し、点数計算を行う。
- 次の局へ進む:アガったプレイヤーが親だった場合、親が継続。子がアガった場合は親が交代する。
麻雀はルールを覚えると奥深い戦略が楽しめるゲームです。まずは基本のルールを理解し、実際にプレイしながら覚えていきましょう。
麻雀役一覧:初心者でも覚えやすい役3選
麻雀では、役がなければアガることができません。役は全部で37種類あり、中には難易度の高いものもあります。しかし、初心者のうちは簡単に覚えられて使いやすい役から覚えるとスムーズにプレイできます。ここでは、初心者向けにおすすめの役を3つ紹介します。
1. リーチ
リーチは、初心者が最も簡単に狙える役のひとつです。自分の手牌があと1枚でアガれる状態(テンパイ)になったとき、「リーチ!」と宣言し、1,000点棒を場に置きます。リーチをすると、あとはツモやロンを待つだけでアガれます。
リーチのメリットは、牌の組み合わせに関係なく成立することです。また、「一発(イッパツ)」や「裏ドラ」がつくことで、得点が大きく伸びる可能性もあります。ただし、リーチ後は手牌の変更ができず、危険な牌を切ってしまうリスクもあるため注意が必要です。
2. 役牌(ヤクハイ)
役牌は、特定の牌を3枚そろえるだけで成立する簡単な役です。役牌には以下の種類があります。
・三元牌(白・發・中)
・場風牌(その局の風:東場なら東、南場なら南)
・自風牌(自分の座っている位置の風)
例えば、東場で自分が東家の場合、「東」を3枚そろえれば役牌が成立します。鳴いて(ポンして)も成立するため、初心者でも比較的アガりやすい役です。
3. 断么九(タンヤオ)
タンヤオは、手牌のすべてを「2~8の数牌」だけで構成すると成立する役です。字牌(東南西北・白發中)や1・9の数牌を一切含まないのが特徴です。
タンヤオの強みは、鳴いても成立することです。そのため、積極的にポンやチーをして、すばやくアガリを狙うことができます。手軽に作れるので、初心者が最初に狙う役としても適しています。
まずはこれらの役を覚え、実際にゲームで使いながら役の種類を増やしていきましょう。
初心者がやってはいけないこと
麻雀を始めたばかりの初心者は、ルールを覚えることに集中しがちですが、いくつかの注意点もあります。特に、やってはいけないことを知っておくことで、よりスムーズに上達できます。ここでは、初心者が避けるべき行動を紹介します。
鳴きすぎる
ポンやチーを頻繁にすると、手牌の自由度が下がり、役を作るのが難しくなります。特に、リーチやピンフなどの役は鳴くと成立しないため、安易な鳴きは避けるべきです。鳴きを使う際は、本当に必要な場面かどうかを慎重に判断しましょう。
無計画に捨て牌を選ぶ
何も考えずに捨て牌を選ぶと、相手に自分の手牌が読まれやすくなり、振り込み(他家にアガられること)のリスクが高まります。捨て牌の選択は慎重に行い、安全牌(他のプレイヤーがすでに捨てている牌)を意識することが重要です。
マナーを守らない
麻雀は対人ゲームのため、マナーが非常に大切です。例えば、牌を雑に扱う、対局中にスマホをいじる、考えすぎて長考しすぎるなどの行為は、周囲のプレイヤーに迷惑をかけます。気持ちよくプレイするためにも、基本的なマナーを守ることを心がけましょう。
これらの点を意識すれば、より楽しく麻雀をプレイできるようになります。まずは基本ルールを覚え、落ち着いてゲームを進めることが大切です。
ルールが難しいと感じる理由と解決策
麻雀は奥深いゲームであるため、初心者の多くが「ルールが難しい」と感じてしまいます。しかし、実際にはポイントを押さえて学べば、意外とスムーズに理解できるようになります。ここでは、麻雀のルールを難しく感じる主な理由と、それを克服するための解決策を紹介します。
麻雀が難しいと感じる理由
麻雀を難しく感じる原因はいくつかあります。特に、初心者がつまずきやすいポイントは以下の通りです。
- 覚えることが多い
- 牌の種類や役のルール、点数計算など、最初に学ぶべきことが多いため、混乱しやすい。
- ゲームの流れが複雑
- 「ツモ」「ロン」「鳴き」「親の移動」など、進行ルールが多く、一度に理解するのが難しい。
- 専門用語が多い
- 一般的なゲームと異なり、特殊な用語が頻繁に使われるため、最初は意味を理解しづらい。
- 点数計算が難しい
- 役ごとの翻数や符計算など、スコアの仕組みが複雑で、慣れるまでは計算が大変。
ルールを理解しやすくする解決策
難しさを感じるポイントごとに、具体的な解決策を紹介します。
1. まずは最低限のルールを覚える
- いきなりすべてのルールを覚えようとすると挫折しやすいため、基本的な「アガリの形」と「簡単な役」から学ぶ。
- 「リーチ」「タンヤオ」「役牌」などの簡単な役を先に覚えると、実戦でも使いやすい。
2. ゲームの流れを実際に体験する
- 理論だけでなく、実際にプレイしながら学ぶと理解しやすくなる。
- CPU戦や友人とのカジュアルな対戦で、ゲームの流れに慣れることが大切。
3. 専門用語の意味をリスト化する
- 「ツモ」「ロン」「ドラ」など、よく使われる用語を一覧でまとめておくと、プレイ中に困らない。
- スマホで検索しながらプレイするのも有効。
4. 点数計算は最初はアプリや表を活用する
- 初心者のうちは、点数計算をすべて暗記するのではなく、点数早見表やアプリの自動計算機能を利用する。
- ある程度慣れたら、基本的な点数計算の仕組みを学ぶとよい。
麻雀のルールは、すべてを一度に覚える必要はありません。少しずつ学んで実践を繰り返すことで、自然に理解できるようになります。
よく出る「意味不明」な専門用語
麻雀には、多くの専門用語が存在します。初心者にとっては、聞き慣れない言葉が多いため、最初は意味が分からず戸惑うこともあるでしょう。ここでは、麻雀で頻繁に使われる専門用語と、その意味をわかりやすく解説します。
基本用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ツモ | 自分で山から引いた牌でアガること |
| ロン | 他のプレイヤーの捨てた牌でアガること |
| ドラ | アガリ時に持っていると点数が上がる牌 |
| リーチ | あと1枚でアガれるときに宣言し、固定の点数を場に出す行為 |
| 鳴き | 「ポン」「チー」「カン」の総称で、他プレイヤーの捨て牌を利用すること |
ゲーム進行に関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 親 | 最初に配牌を受け取り、アガると点数が高くなるプレイヤー |
| 子 | 親以外のプレイヤー |
| 風牌 | 東・南・西・北の字牌で、状況により役になる |
| 流局 | 誰もアガらずに局が終了すること |
| 供託 | リーチなどで場に出した点棒 |
役に関する用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 役牌 | 特定の字牌(白・發・中など)を刻子でそろえると成立する役 |
| 平和(ピンフ) | 順子と雀頭で構成されたシンプルな役 |
| 七対子(チートイツ) | 7組の対子(2枚のペア)だけで構成された役 |
| 三色同順 | 萬子・筒子・索子の3種類で同じ数字の順子をそろえた役 |
| 一気通貫 | 同じ種類の1~9の牌を順番にそろえた役 |
麻雀の専門用語は、最初は難しく感じるかもしれませんが、プレイしながら使っていくうちに自然と覚えられます。初心者のうちは、よく使われる言葉だけでも把握しておくとスムーズに進められるでしょう。
初心者向けゲームアプリの選び方
麻雀を覚えるためには、実際にプレイすることが最も効果的です。しかし、いきなり対人戦に挑戦するのは不安に感じる人もいるかもしれません。そこで、初心者向けの麻雀ゲームアプリを活用するのがおすすめです。ここでは、初心者が麻雀アプリを選ぶ際のポイントを紹介します。
初心者向け麻雀アプリの選び方
初心者にとって、以下のような機能があるアプリが理想的です。
- チュートリアルが充実している
- 初めての人でもルールを学びながらプレイできる解説付きのアプリを選ぶ。
- サポート機能がある
- 役の説明や待ち牌の表示機能があると、プレイしながら学ぶことができる。
- 初心者向けの対戦モードがある
- CPU戦や段位別のマッチングがあると、実力に応じたプレイが可能。
- 点数計算を自動で行ってくれる
- 点数計算が難しい初心者でも、スムーズにゲームを進められる。
おすすめの初心者向け麻雀アプリ
| アプリ名 | 特徴 |
|---|---|
| ジャンナビ麻雀 | シンプルな操作性と見やすい画面が魅力 |
| 雀魂(じゃんたま) | 可愛いキャラとともに麻雀を楽しめる |
| セガNET麻雀 MJ | 本格的な麻雀を学びたい人向け |
| 麻雀格闘倶楽部 | 実力に応じた対戦モードがある |
| ヤムチャ師匠の麻雀講座 | 麻雀の基礎を学べる学習特化型アプリ |
初心者は、まずはCPU戦や解説付きのモードで練習し、徐々にオンライン対戦に挑戦するとよいでしょう。適切なアプリを選び、自分のペースで麻雀を学んでいきましょう。
麻雀のルールを簡単に覚えるためのコツ

点数計算の基本
麻雀では、アガったときに得られる点数が決まっています。しかし、初心者にとって点数計算は難しく感じることが多いです。基本を押さえれば理解しやすくなるので、ここでは点数計算の仕組みをわかりやすく解説します。
点数計算の流れ
麻雀の点数計算は、以下の3つのステップで行います。
- 翻(ハン)の数を決める
- 役の合計で「何翻(ハン)」の手なのかを確認する。
- 符(フ)の計算をする
- 手牌の形やアガり方に応じて符を計算する。
- 点数表に当てはめて計算する
- 翻数と符の組み合わせを点数表に照らし合わせて点数を決める。
翻(ハン)とは?
翻(ハン)とは、アガリ役の強さを示す単位です。役ごとに決まった翻数があり、それを合計して計算します。例えば、以下のようになります。
| 役名 | 翻数 | 鳴き |
|---|---|---|
| リーチ | 1翻 | × |
| タンヤオ | 1翻 | 〇 |
| ピンフ | 1翻 | × |
| 三色同順 | 2翻 | 〇 |
| 混一色 | 3翻 | 〇 |
翻数が高いほど点数も高くなります。
符(フ)とは?
符(フ)とは、手牌の形やアガり方によって加算される点数の単位です。符は以下のルールに従って計算します。
| 条件 | 符数 |
|---|---|
| 面前ロン | 10符 |
| ツモアガリ | 2符 |
| 暗刻(同じ牌を3枚持つ) | 4符(中張牌)/8符(ヤオ九牌) |
| 明刻(ポンした刻子) | 2符(中張牌)/4符(ヤオ九牌) |
| 雀頭が役牌 | 2符 |
符の合計は切り上げ(10符単位)で計算されます。
点数表を使った計算
翻数と符を求めたら、点数表を使って最終的な得点を決定します。
| 翻数/符 | 20符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1翻 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | 3,000 |
| 2翻 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 4,800 | 6,000 |
| 3翻 | 3,900 | 5,200 | 7,700 | 9,600 | 12,000 |
| 4翻 | 7,700 | 8,000 | 11,000 | 12,000 | 18,000 |
このように、翻数と符の組み合わせによって点数が決まります。
初心者のうちは、点数計算アプリや早見表を活用すると便利です。ゲームに慣れてきたら、少しずつ計算方法を覚えていきましょう。
鳴き(チー・ポン・カン)のルール
麻雀では、自分の手だけで役を作る以外に、他のプレイヤーの捨て牌を利用して手を進める方法があります。それが「鳴き(ナキ)」です。鳴きをうまく使えばスピーディにアガれるようになりますが、ルールを理解せずに多用すると逆効果になることもあります。ここでは、「チー・ポン・カン」のルールと注意点を解説します。
鳴きの基本ルール
鳴きには3種類あります。それぞれの特徴を押さえましょう。
| 鳴きの種類 | 条件 | 役が成立するか |
|---|---|---|
| チー | 左隣のプレイヤーの捨て牌で順子(同じ種類の数牌の連続した3枚)を作る | 〇(ただし一部の役は不可) |
| ポン | 誰かの捨て牌で刻子(同じ牌3枚)を作る | 〇 |
| カン | 誰かの捨て牌 or 自分の手牌で4枚揃える | △(種類による) |
鳴きの詳細ルール
チー
- 「1-2」を持っていて、左隣のプレイヤーが「3」を捨てた場合に鳴くことができる。
- 鳴けるのは左隣のプレイヤーの捨て牌のみ。
ポン
- 「5-5」を持っていて、誰かが「5」を捨てたら鳴ける。
- 誰の捨て牌でもポンが可能。
カン
カンには3種類あり、ルールが少し複雑です。
| カンの種類 | 条件 | 特徴 |
|---|---|---|
| 暗槓(アンカン) | 自分の手牌だけで4枚そろえる | 鳴き扱いにならず、リーチ後でも可能 |
| 大明槓(ダイミンカン) | 誰かの捨て牌を使って4枚そろえる | 他のプレイヤーにチャンスを与えるためリスクあり |
| 小明槓(ショウミンカン) | すでにポンしている牌を、もう1枚引いてカンする | ドラが増えるため点数アップのチャンス |
鳴きのメリットとデメリット
メリット
- アガりが早くなる:手牌の完成が早まり、勝利しやすくなる。
- 相手にプレッシャーを与えられる:他のプレイヤーが警戒し、攻めにくくなる。
デメリット
- リーチができなくなる:リーチは門前(鳴きなし)でなければ成立しない。
- 役の幅が狭まる:ピンフなどの役は鳴くと成立しなくなるため、点数が低くなりがち。
- 相手に手牌が読まれやすい:鳴いた牌が公開されるため、相手に手を読まれるリスクがある。
初心者は、まずは鳴きをせずに門前で手を作る練習をするとよいでしょう。慣れてきたら、状況に応じて鳴きを活用するのがおすすめです。
役なしでアガれない!覚えるべきルール
麻雀では、「役がないとアガれない」 というルールがあります。初心者のうちは、手牌がそろっているのにアガれないことがあり、戸惑うこともあるでしょう。ここでは、役なしでアガれない理由と、覚えておくべき基本ルールを解説します。
役なしでアガれない理由
- 麻雀は役を作るゲームだから
- 単に牌をそろえるだけではなく、役の条件を満たさないとアガれない。
- 最低でも1翻(ハン)が必要
- どんなに完成された形でも、1翻以上の役がなければアガりにはならない。
初心者が覚えるべき簡単な役
| 役名 | 条件 |
|---|---|
| リーチ | テンパイしたら宣言する |
| 役牌 | 白・發・中を刻子でそろえる |
| タンヤオ | 1・9・字牌を使わずに手を作る |
最初は、これらの簡単な役から覚えて、スムーズにアガれるようにしましょう。
リーチとドラの仕組み
麻雀にはさまざまなルールがありますが、ゲームの流れを大きく左右するのが「リーチ」と「ドラ」です。どちらも点数を大きく伸ばすチャンスとなる要素ですが、正しく理解していないと効果的に活用できません。ここでは、リーチとドラの仕組みについて詳しく解説します。
リーチの仕組み
リーチとは、テンパイ(あと1枚でアガれる状態)したときに宣言することで成立する役です。リーチをすることで、手が完成しなくても1翻(ハン)が確定します。リーチをかけることで、得点アップの可能性が高まり、プレッシャーをかける効果もあります。
リーチの基本ルールは以下の通りです。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| テンパイしていること | あと1枚でアガれる状態である必要がある |
| 門前であること | ポンやチーをしていない状態(鳴いていない状態)であること |
| 1,000点棒を供託する | リーチ宣言時に1,000点棒を場に出す |
| 以降、手牌を変えられない | リーチ後はツモった牌をそのまま捨てなければならない |
リーチをかけるメリットは、1翻が確定するだけでなく、「一発」や「裏ドラ」といったボーナスの可能性が生まれる点にあります。ただし、リーチ後は手牌を変更できず、振り込み(相手にアガられること)のリスクが高まるため、慎重な判断が必要です。
ドラの仕組み
ドラとは、アガったときに持っていると得点がアップするボーナス的な牌のことです。ドラ自体に役の効果はありませんが、ドラを活かすことで高得点を狙いやすくなります。
ドラには以下の種類があります。
| ドラの種類 | 説明 |
|---|---|
| 表ドラ | 局ごとに決められる通常のドラ |
| 裏ドラ | リーチでアガったときに追加でめくるドラ |
| 槓ドラ | カンをしたときに追加されるドラ |
| 赤ドラ | もともと赤色の牌として特別に設定されているドラ |
ドラの増加は得点アップの大きな要因となるため、ドラをうまく活用することが戦略のカギになります。ただし、ドラを持っていることを相手に悟られると警戒されやすくなるため、使い方には注意が必要です。
戦略と流れのポイント
麻雀では、単純にアガることを目指すだけでなく、場の流れや戦略を意識することが重要です。初心者のうちは「とにかく手を進めればいい」と考えがちですが、状況を見極めることで勝率が大きく変わります。ここでは、戦略とゲームの流れのポイントについて解説します。
ゲームの流れを意識する
麻雀の1局は、以下のような流れで進行します。
- 親と席順を決める
- 配牌(手牌を配る)を行う
- 親からツモと打牌を繰り返す
- 役を完成させたプレイヤーがアガる
- アガリや流局後に点数の計算を行う
この流れを理解した上で、局の進行に応じた打ち方を考えることが重要です。
戦略の基本
麻雀では、ただアガりを目指すのではなく、状況に応じた戦略を取ることが必要です。
- 手役を意識する
- どの役を狙うのかを早い段階で決めることで、効率的に手を進められる。
- 例えば、ドラを活用するなら「タンヤオ」と組み合わせると高得点を狙いやすい。
- 防御を考える
- 相手の捨て牌を見て、危険な牌を切らないようにする。
- 「ベタオリ」(安全な牌だけを捨てて守る戦略)を取ることで、大きな失点を防げる。
- 鳴きを使いこなす
- 鳴きをすると手を早く進められるが、リーチができなくなるため、得点が低くなりがち。
- 鳴きをする場合は、「役牌」や「対々和(トイトイ)」など、鳴いても成立する役を意識する。
これらのポイントを押さえておくと、より戦略的に麻雀を楽しめるようになります。
初心者向け!おすすめゲームアプリ
麻雀を覚えたばかりの初心者にとって、実戦経験を積むことはとても重要です。しかし、リアルの対局ではルールをすぐに確認できないため、初心者にはハードルが高い場合もあります。そこでおすすめなのが、麻雀ゲームアプリです。ここでは、初心者に適した麻雀アプリを紹介します。
初心者向けアプリの選び方
初心者が麻雀アプリを選ぶ際には、以下のポイントを重視すると良いでしょう。
- チュートリアルが充実しているか
- ルールや役を詳しく説明してくれる機能があるかを確認する。
- 操作が簡単で見やすいか
- 牌の配置や操作性が直感的で、プレイしやすいかをチェックする。
- 初心者向けの対戦モードがあるか
- CPU戦や初心者向けルームがあると、気軽に練習できる。
おすすめの麻雀アプリ
| アプリ名 | 特徴 |
|---|---|
| ジャンナビ麻雀オンライン | シンプルな操作性と初心者向け機能が充実 |
| 雀魂(じゃんたま) | 可愛いキャラクターと遊びやすいUI |
| セガNET麻雀 MJ | 初心者向けのトレーニングモードが充実 |
| 麻雀格闘倶楽部SP | プロ雀士との対戦も可能 |
それぞれのアプリには特徴があるため、自分に合ったものを選びましょう。
麻雀アプリの活用方法
麻雀アプリを使うことで、初心者でも気軽に対局の経験を積めます。以下のような活用方法がおすすめです。
- CPU戦で基本ルールを確認する
- まずはコンピューター相手にプレイし、ルールを覚える。
- オンライン対戦で実戦感覚を養う
- 実際の対局に近い環境でプレイし、駆け引きの練習をする。
- 牌効率や点数計算の練習をする
- 「何切る」問題を解いたり、点数計算の練習をしたりして理解を深める。
麻雀は、経験を積むほど上達するゲームです。初心者のうちはミスをしても気にせず、ゲームアプリを活用しながら少しずつ学んでいきましょう。
麻雀のルールを簡単に理解するポイントまとめ
記事のポイントをまとめます。
- 麻雀は4人で対戦する戦略性の高いゲーム
- 牌を組み合わせて役を作り、アガることで得点を獲得する
- 牌の種類には数牌・字牌・赤牌がある
- アガリの形は「4面子1雀頭」が基本
- 役なしではアガることができないため、最低1翻が必要
- 「リーチ」「役牌」「タンヤオ」は初心者でも覚えやすい役
- 点数計算は翻数と符の組み合わせで決まる
- リーチをすると得点アップのチャンスが広がる
- ドラを持っていると得点が高くなるが、役にはならない
- 鳴き(チー・ポン・カン)を使うと手を進めやすいが制約もある
- 安易な鳴きは役を狭めるため、慎重に判断するべき
- 捨て牌の選び方が重要で、危険牌を避けることが防御につながる
- 戦略を考えながら手を進めることで勝率が上がる
- 初心者はアプリを活用しながらルールを覚えるのがおすすめ
- ルールを一度に覚えようとせず、実戦を通じて少しずつ習得する