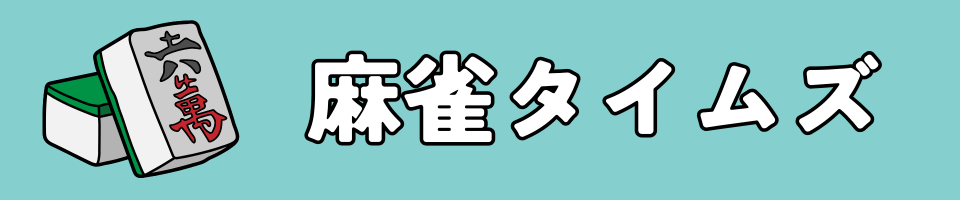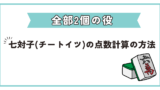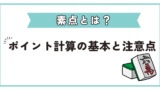麻雀をプレイしていると、「どこまでツモを続ければいいの?」と疑問に感じたことはありませんか?特に、終盤に差し掛かるとツモのタイミングや残りの牌が気になってくるものです。この記事では、麻雀における「どこまで引くか」の基本ルールを分かりやすく解説します。
麻雀では、牌山のすべてを引くわけではなく、14枚の牌を残しておく決まりがあります。この残された牌は「王牌(ワンパイ)」と呼ばれ、ドラ表示牌やカンの際に使用されるリンシャン牌が含まれています。
さらに、牌山の最後にツモることができる牌は「ハイテイ牌」と呼ばれ、この牌で和了すると特別な役が付くこともあります。ハイテイの役やその狙い方についても詳しく説明していきます。
また、ゲームの進行をスムーズに行うためには、正しい「山の取り方」を知ることが重要です。親のサイコロの振り方から始まる山の取り方やツモの進行方法についても丁寧に解説します。
この記事を読むことで、麻雀の終盤でのツモのルールやハイテイの役、山の取り方に関する疑問がスッキリ解消できるはずです。それでは、麻雀の基本ルールと戦略について一緒に学んでいきましょう。
- 麻雀でどこまでツモを続けるかの基本ルール
- 流局やハイテイ牌に関する役と得点の仕組み
- 王牌(ワンパイ)の役割と山の取り方
- 流局時の親の扱いや点数のやり取りのルール
麻雀の牌はどこまで引く?流局とハイテイの関係

流局とは?
流局とは、麻雀の一局が誰も和了(アガリ)することなく終了することを指します。麻雀の基本ルールとして、各プレイヤーが順番に牌を引いて(ツモ)いき、特定の役を揃えて和了することを目指します。しかし、全員が牌を引き終わっても誰も和了できなかった場合、その局は流局となります。
流局が発生した場合、いくつかのルールに従って処理が行われます。まず、流局時に聴牌(テンパイ)しているプレイヤーは、自分の手牌を公開して聴牌であることを示します。聴牌しているプレイヤーが複数いる場合、その人数に応じてノーテン(聴牌していない)プレイヤーから点棒の支払いが発生します。例えば、1人が聴牌している場合は、ノーテンの3人がそれぞれ1,000点ずつ支払います。この点数のやり取りを「ノーテン罰符」と呼びます。
親の扱いも流局によって異なります。親が聴牌している場合は「連荘(レンチャン)」といい、次の局でも引き続き親を務めます。一方で、親がノーテンだった場合は「親流れ」となり、親は次のプレイヤーに交代します。この親の交代ルールは、麻雀の戦略に大きな影響を与える要素の一つです。
なお、流局には通常の流局と「途中流局」の2種類があります。途中流局とは、局の途中で特定の条件が満たされた場合に発生する流局です。例えば、「九種九牌(キュウシュキュウハイ)」や「四風連打(スーフーレンダ)」といった特殊な状況がこれに該当します。
流局は、単なる引き分けの場面ではなく、点数や親の流れに影響を与える重要な局面です。そのため、プレイヤーは流局のルールを正確に理解し、状況に応じた戦略を立てることが求められます。
どこまでツモる?
麻雀では、牌山のすべての牌をツモることはありません。どこまでツモるかというと、牌山のうち14枚を残すところまでツモを行います。この残された14枚の牌は「王牌(ワンパイ)」と呼ばれ、ドラ表示牌やリンシャン牌として使われるため、プレイヤーがツモることはできません。
牌山の積み方は、2段×17枚で形成され、合計34枚の牌山が4つ作られます。ツモは反時計回りに行われ、親を含む4人のプレイヤーが順番に牌を引いて進行します。配牌が終わった後、親は14枚の手牌から1枚を捨ててゲームが開始され、その後はツモと捨牌を繰り返していきます。
ツモの回数は、カン(槓)やポンなどの鳴きによって変動することもあります。特にカンが発生した場合、王牌からリンシャン牌をツモることでツモ回数が増えるため、どこまでツモるかが状況によって変わることもあります。ただし、王牌の14枚は必ず残るため、基本的なツモの範囲は変わりません。
流局が発生するのは、最後のツモ牌で誰も和了できなかった場合です。このツモ牌は「海底牌(ハイテイハイ)」と呼ばれ、特別な役が付くこともあります。ツモの終わりが近づくと、プレイヤーは流局を避けるために積極的に聴牌を目指す戦略を取ることが多くなります。
麻雀のゲーム進行を理解するためには、この「どこまでツモるのか」という基本的なルールを正確に把握することが重要です。ツモの範囲を理解することで、ゲーム終盤の戦略や点数のやり取りもスムーズに進めることができます。
ハイテイとは?
ハイテイとは、麻雀において最後にツモられる牌、つまりその局でツモ可能な最終牌を指します。このハイテイでツモ和了(ツモアガリ)すると「海底撈月(ハイテイラオユエ)」という役が付き、追加の得点が加算されます。逆に、ロン和了(他人の捨て牌で和了)した場合は「河底撈魚(ホウテイラオユ)」という別の役が適用されます。
ハイテイ牌の位置は、局の進行やカンの回数によって変動します。カンが行われるたびにツモの順番がずれ、王牌の位置も変わるため、どの牌がハイテイ牌になるかは状況次第です。これにより、終盤の戦略として、ハイテイ牌を狙ってツモ和了を目指すプレイヤーも少なくありません。
ハイテイ役の魅力は、その希少性にあります。ツモの最後の1枚で和了する機会は限られており、その分得点も特別なものとなります。ただし、ハイテイを狙うためには、自分の手牌を聴牌状態に保ちつつ、他のプレイヤーに和了されないよう注意する必要があります。これは非常に高いリスクを伴う戦略でもあります。
一方で、ハイテイ牌には注意点もあります。最後のツモ牌であるため、このタイミングで和了できなかった場合は流局が確定します。また、ハイテイ牌を狙うあまり、無理に手牌を進めると逆に点数を失うリスクもあります。そのため、ハイテイを意識した戦略は、状況を見極めた上で慎重に行うことが求められます。
このように、ハイテイは麻雀の終盤を彩る重要な要素であり、適切に活用することでゲームの流れを大きく変える可能性を秘めています。
王牌(ワンパイ)との関連性
王牌(ワンパイ)は、麻雀の進行や役の成立に大きく関わる重要な要素です。王牌とは、牌山からツモられずに残される14枚の牌のことを指し、この中にはドラ表示牌やリンシャン牌、カンドラ表示牌などが含まれます。これらの牌はゲーム進行中に直接使用されることはなく、特定のルールや状況でのみ関与します。
まず、王牌は流局と密接に関係しています。麻雀の一局でツモが進む中、王牌の14枚を残した状態で誰も和了しなければ、その局は流局となります。つまり、どこまでツモを続けるかは王牌の存在によって決まっているのです。プレイヤーが最後にツモることができる牌は、王牌の直前の牌であり、この牌は「海底牌(ハイテイハイ)」と呼ばれます。
さらに、王牌に含まれるドラ表示牌は得点に直接影響を与えます。ドラは役の得点を増加させる効果があるため、プレイヤーは自分の手牌に対応するドラを含めることで高得点を狙うことができます。このため、王牌の位置やドラの種類を意識することは、戦略的に非常に重要です。
加えて、カンを行った場合に引くリンシャン牌も王牌から供給されます。カンを行うことで新たな牌を王牌からツモるため、王牌の消費が進み、結果として流局までのツモ回数が変動します。このように、王牌は局の進行だけでなく、役の成立や点数の変動にも大きな影響を与える要素です。
総じて、王牌は麻雀の進行をコントロールする基盤となる存在です。プレイヤーは王牌の構成や位置を理解することで、より効果的な戦略を立てることができるでしょう。
流局時の親の扱いと連荘の決まり
麻雀における流局時の親の扱いと連荘(レンチャン)のルールは、ゲームの流れや戦略に大きな影響を与えます。流局とは、誰も和了せずに局が終了することを指しますが、その際の親の状況によって次の局の進行が変わります。
流局時に親が聴牌(テンパイ)している場合は連荘となり、次の局でも引き続き親を務めます。連荘が続くことで親の順番が固定され、親は得点の面で有利な立場を維持できます。麻雀では親のツモアガリは子よりも得点が高くなるため、連荘を続けることで大きな得点を稼ぐチャンスが増えます。このため、親は流局時に聴牌することを目指して手牌を進めることが重要です。
一方で、流局時に親がノーテン(聴牌していない)だった場合は流れ、次のプレイヤーに親権が移ります。親が流れることで新たな局が始まり、ゲームの流れも変わってきます。親が変わることは得点面での有利さを失うことを意味するため、親はできる限り聴牌を維持して連荘を狙う戦略を取るのが一般的です。
なお、流局時の親の扱いにはローカルルールが存在することもあります。例えば、特定のルールでは親が聴牌していても親流れとなる場合や、一定回数の連荘後には強制的に親を交代させるルールもあります。これらのルールは事前に確認しておくことが重要です。
親の連荘は単にゲームの進行に影響を与えるだけでなく、戦略や点数の管理にも直結します。特に競技麻雀では、この親の扱いを理解し、適切な戦略を取ることが勝敗を分ける重要な要素となります。
流局時の点数のやり取り
麻雀における流局時の点数のやり取りは、「ノーテン罰符」として知られ、ゲームのスコアに直接影響します。流局とは、誰も和了せずに一局が終了することを指し、その際に各プレイヤーの聴牌(テンパイ)状況によって点数のやり取りが発生します。
流局時に聴牌しているプレイヤーがいる場合、ノーテンのプレイヤーから点数が支払われます。具体的には、流局時に聴牌していたプレイヤー全員に対して合計3,000点の支払いが行われます。支払いの内訳は以下の通りです。
- 聴牌者が1人の場合:ノーテンの3人がそれぞれ1,000点ずつ支払う。
- 聴牌者が2人の場合:ノーテンの2人がそれぞれ1,500点ずつ支払う。
- 聴牌者が3人の場合:ノーテンの1人が3,000点を支払う。
この点数のやり取りを「ノーテン罰符」と呼び、聴牌していなかったプレイヤーに対するペナルティとして機能します。聴牌しているだけで点数を得られるため、終盤での聴牌は非常に重要な戦略となります。
一方で、全員がノーテンだった場合は点数のやり取りは発生しません。ただし、この場合でも親の連荘や親流れといった進行ルールには影響を与えるため、全員ノーテンで流局する状況も戦略的に考慮する必要があります。
また、流局時に供託されているリーチ棒(1000点棒)はアガリが発生しないため、そのまま次の局に持ち越されます。次の局でアガったプレイヤーがこれを回収できるため、流局後の局では供託棒が増えることも少なくありません。
流局時の点数のやり取りは、単に罰符としての意味だけでなく、ゲーム全体の戦略にも大きく影響します。特に点数が僅差の場合、流局による点数移動が勝敗を左右することもあるため、流局時のルールを正確に理解し、状況に応じた最適な判断を下すことが求められます。
途中流局のルール
途中流局とは、麻雀の局が途中で強制的に終了する特別なルールのことを指します。通常、麻雀の一局は誰かが和了するか、全員がツモ牌を引き終えて流局するまで続きますが、特定の条件が発生するとその局は途中で終了し、最初からやり直すことになります。途中流局のルールは主に以下のようなものがあります。
1. 九種九牌(キュウシュキュウハイ)
最初の配牌時に、么九牌(ヤオチューハイ)と呼ばれる1と9の数牌、東南西北の風牌、白・發・中の三元牌が9種類以上含まれている場合、九種九牌を宣言することで局を流すことができます。ただし、宣言しなければそのまま局を続行することも可能で、国士無双(コクシムソウ)という役満を狙うこともできます。
2. 四風連打(スーフーレンダ)
1巡目の最初の捨牌で、4人全員が同じ種類の風牌を捨てた場合、この局は四風連打として途中流局となります。これは偶然発生することが多いですが、狙って発生させるのは難しい特殊な状況です。
3. 四開槓(スーカイカン)
1局の間に4回カンが行われた場合、その局は四開槓として流局します。ただし、1人のプレイヤーが4回カンを行った場合は例外で、局は続行されます。この場合、四槓子(スーカンツ)という役満を狙うチャンスとなります。
4. 三家和(サンチャホー)
1つの捨牌に対して、3人のプレイヤーが同時にロンを宣言した場合、三家和として途中流局となります。麻雀ではロンの権利は最も上家に近いプレイヤーに与えられるため、このような状況は極めて稀ですが、発生すると局は即座に終了します。
5. 4人リーチ
全員がリーチを宣言した場合、その局は途中流局となるルールもあります。これはローカルルールとして採用されている場合が多く、公式戦では必ずしも適用されないため、事前に確認することが大切です。
途中流局が発生した場合、通常は点棒のやり取りは行われず、親も流れません。局は最初からやり直され、次の配牌が行われます。ただし、ローカルルールによっては点棒のやり取りが発生する場合もあるため、プレイする前にルールの確認をしておくことが重要です。
麻雀の牌はどこまで引く?山の取り方

牌山の積み方と残る14枚(王牌)
麻雀をプレイする上で、牌山の積み方とその中に残される14枚の牌である王牌(ワンパイ)の理解は非常に重要です。牌山は麻雀牌を使用して構築され、ゲームの進行に不可欠な要素となります。ここでは、牌山の基本的な積み方と、なぜ14枚が王牌として残るのかについて解説します。
牌山の基本的な積み方
麻雀牌は全部で136枚(または赤ドラを含めるとさらに増えることもあります)あり、これを4人のプレイヤーが順番に積み上げます。牌山は2段構成で、1列あたり17枚、合計34枚の牌を2段に積むことで、4つの牌山が完成します。これにより、136枚の牌が正確に配置されることになります。
積み上げた牌山のどこからツモを開始するかは、親プレイヤーがサイコロを振って決定します。サイコロの出目に従って、牌山の切れ目を作り、そこから配牌やツモが始まります。
残る14枚の王牌(ワンパイ)とは?
牌山の中で、最後に残される14枚の牌を王牌(ワンパイ)と呼びます。これらの牌はゲームの進行中にプレイヤーがツモることはできません。王牌の主な用途は以下の通りです。
- ドラ表示牌(1枚)
ドラ表示牌は、得点を増加させる「ドラ」の存在を示します。プレイヤーはドラに対応する牌を手牌に含めることで、和了時の得点を上げることができます。 - 裏ドラ表示牌(1枚)
リーチをかけて和了した場合にのみ適用されるドラ表示牌です。裏ドラも得点を増加させる要素となります。 - リンシャン牌(4枚)
カン(槓)を行った際に引く牌です。これにより、カンの後でもツモ回数が維持されます。 - カンドラ表示牌(4枚)および槓裏ドラ表示牌(4枚)
カンを行った後に新たに追加されるドラ表示牌と裏ドラ表示牌です。
これらの役割を果たすため、王牌は必ず14枚が残される仕組みになっています。王牌の存在によって、全ての牌がツモられることなく、ゲームの戦略性が増すのです。
牌山の積み方と王牌の理解は、麻雀の基本中の基本です。これを正しく把握することで、ゲームの進行がスムーズになり、戦略的なプレイも可能になります。
山の取り方とツモの進行
麻雀における「山の取り方」と「ツモの進行」は、ゲームの基本的な流れを理解する上で欠かせない要素です。牌山のどこから牌を取るのか、そしてどのようにツモが進行していくのかを知ることで、より戦略的なプレイが可能となります。
山の取り方の基本
牌山は4人のプレイヤーによって2段×17枚の形で積み上げられます。この牌山からどこを切り出してツモを開始するかは、親プレイヤーがサイコロを振ることで決定されます。サイコロの出目に従って、親の前から右回りに数えていき、指定された場所から配牌が始まります。
配牌は、最初に親が14枚の牌を取り、他のプレイヤーは13枚ずつ取ります。この配牌が完了した時点でゲームが開始され、親が不要な1枚を捨てることでツモの順番が回り始めます。
ツモの進行方法
ツモは反時計回りに進行します。親が最初に1枚の牌を捨てた後、次は南家、西家、北家の順に牌山から1枚ずつツモを行い、それぞれ不要な牌を捨てます。このサイクルを繰り返しながら、プレイヤーは手牌を揃えていきます。
ツモの際にはいくつかの注意点があります。
- カンの影響
カン(槓)を行った場合、王牌からリンシャン牌をツモることになります。カンを行うことでツモの順番や牌山の消費が変化するため、流局のタイミングにも影響を与えます。 - 王牌の14枚を残す
麻雀では、牌山の全てをツモることはなく、王牌として14枚を残す必要があります。このため、ツモは王牌直前の牌で終了し、誰も和了できなかった場合は流局となります。
ツモ進行の戦略的要素
ツモの進行を理解することは、麻雀の戦略に直結します。例えば、終盤に近づくにつれて残りのツモ回数を意識し、聴牌(テンパイ)に持ち込むかどうかを判断することが重要です。また、カンを行うタイミングもツモの流れに影響を与えるため、慎重な判断が求められます。
山の取り方とツモの進行は麻雀の基本であり、これをしっかりと理解することで、ゲーム全体の流れを把握しやすくなります。
捨て牌と手牌の関係
麻雀において、捨て牌と手牌の関係はゲームの進行と戦略に大きく影響します。どの牌を捨て、どの牌を手元に残すかを判断することは、和了(アガリ)への道を切り開くための鍵となります。ここでは、捨て牌と手牌の関係性について詳しく解説します。
捨て牌と手牌の基本的な関係
麻雀では、13枚の手牌を持ちながら1枚ツモをして、不要な牌を1枚捨てるという流れを繰り返します。このとき、どの牌を捨てるかが戦略の要となります。捨て牌は自分の手牌の情報を相手に与える手段にもなり、慎重に選ぶ必要があります。
捨て牌は卓の中央に並べられ、「河(ホー)」と呼ばれるスペースに置かれます。通常、6枚ごとに新しい列に並べるのが一般的です。相手の捨て牌を見ることで、そのプレイヤーがどのような役を狙っているのか、どの色の牌を集めているのかを推測することができます。
捨て牌の戦略的な活用
捨て牌の判断は、単なる運ではなく戦略的な要素が強く反映されます。例えば、流局が近づいている場合、無理に和了を目指すのではなく、安全に聴牌してノーテン罰符を避ける選択も有効です。
また、相手の手牌を読んで危険な牌を避けることも重要です。特に終盤では、リスクの高い牌を切らずに守りに徹することで、大きな失点を防ぐことができます。
捨て牌と手牌の関係を理解することで、麻雀の勝率を大きく向上させることができます。これらの要素をバランス良く考慮し、状況に応じた最適な判断を行うことが求められます。
捨てるタイミングが勝敗に影響する
麻雀では、捨て牌のタイミングが勝敗を大きく左右します。一見すると単純な繰り返しのように思える捨て牌ですが、実際には高度な判断力と戦略が求められる場面が多く存在します。
捨て牌の基本的な流れ
麻雀の基本ルールでは、プレイヤーは順番に牌山から1枚ツモし、手牌に加えた後、不要な牌を1枚捨てるというサイクルを繰り返します。この過程で、どのタイミングでどの牌を捨てるかが、最終的な和了の可能性や点数に直結します。
捨て牌のタイミングが重要な理由
- 役の形成に直結する
役を作るためには、特定の牌の組み合わせが必要です。ツモで必要な牌を引いた際、どの牌を残すか、どの牌を捨てるかを適切に判断することで、効率的に役を完成させることができます。 - 相手の動きを読む
捨て牌のタイミングによって、相手に与える情報が変わります。例えば、序盤で特定の牌を捨てることで相手に手牌の構成を悟られる可能性があります。一方で、相手の捨て牌を観察することで、相手がどのような役を狙っているのかを推測し、危険な牌を避けることも可能です。 - 防御と攻撃のバランス
終盤に差し掛かると、無理に攻めるのではなく、防御的なプレイに切り替えることも重要です。相手がリーチをかけた場合、安全牌を確保しておくことで大きな失点を防ぐことができます。捨て牌のタイミングを誤ると、不要なリスクを負うことになります。
具体的な戦略例
- 序盤
序盤では手牌の形を整えることに重点を置きます。不要な字牌や孤立した端牌を優先的に捨て、柔軟な手牌構成を目指します。 - 中盤
中盤では、自分の手牌の進行状況と相手の動向を見ながら捨て牌を調整します。相手がリーチをかけていない場合は積極的に攻めることもできますが、リーチがかかった場合には慎重な判断が必要です。 - 終盤
終盤では、防御を意識しながら、安全牌を捨てることが重要です。特に、相手がテンパイしていると予想される場合、無理に和了を狙うのではなく、流局を見据えたプレイも有効です。
ツモと捨て牌のタイミングを正しく理解し、状況に応じて柔軟に対応することで、麻雀の勝率を大きく向上させることができます。
親が聴牌していた場合の流れ
麻雀において親が聴牌(テンパイ)している場合の流れは、ゲームの進行や得点に大きな影響を与えます。親の聴牌状況によって、次の局の親番の継続や点数の変動が決まるため、このルールを正しく理解することが重要です。
親が聴牌している場合の基本ルール
麻雀の一局が流局となった際、親が聴牌している場合には「連荘(レンチャン)」となります。連荘とは、親番が次の局でも継続することを意味します。このルールは親にとって有利な状況を維持するためのものであり、親は連続して親番を務めることで得点のチャンスが増えます。
- 親が聴牌している場合
親は連荘となり、次の局でも親番を継続します。この場合、積み棒(100点棒)が卓に追加され、アガリの際に追加得点が得られることになります。 - 親がノーテン(聴牌していない)場合
親番は流れ、次のプレイヤーに親権が移ります。この場合、親は次の局で子の立場に戻ります。
親の聴牌が与える影響
- 得点の増加
親が連荘することで、積み棒が増え、アガリ時の得点が上昇します。特にツモアガリの場合、全員から追加点を獲得できるため、親番を維持することは非常に有利です。 - ゲームの流れをコントロール
親が連荘することで、ゲームの流れを自分に有利に進めることができます。連続して親番を務めることで、積極的な攻撃が可能になり、対戦相手にプレッシャーを与えることができます。 - 防御的な戦略の必要性
親が聴牌している場合、他のプレイヤーは連荘を阻止するために防御的な戦略を取ることがあります。特に親が積極的に攻めてくる場合、無理に攻めずに守りに徹することが求められます。
親の聴牌はゲーム全体に大きな影響を与えるため、状況に応じた戦略を立てることが重要です。
役無し聴牌でも得点を得られる理由
麻雀において、役が付かない聴牌(テンパイ)でも得点を得られる場合があります。この状況は「形式聴牌」と呼ばれ、特に流局時に重要な役割を果たします。ここでは、役無し聴牌でも得点を得られる理由とその背景について解説します。
形式聴牌とは?
形式聴牌とは、役は成立していないものの、あと1枚で和了できる形が揃っている状態のことを指します。通常、麻雀で和了するためには役が必要ですが、流局時には役の有無に関係なく、聴牌しているだけで得点を得ることができます。
流局時の点数配分
流局時に聴牌しているプレイヤーには、ノーテン罰符として点数が支払われます。具体的には、以下のような点数配分が行われます。
- 聴牌者が1人の場合
ノーテンの3人がそれぞれ1,000点ずつ支払います。 - 聴牌者が2人の場合
ノーテンの2人がそれぞれ1,500点ずつ支払います。 - 聴牌者が3人の場合
ノーテンの1人が3,000点を支払います。
この点数のやり取りは、役の有無に関係なく行われるため、役無しの形式聴牌でも得点を得ることが可能です。
なぜ役無し聴牌でも得点が得られるのか?
- 聴牌を維持する難しさ
流局時に聴牌を維持することは簡単ではありません。手牌の進行や相手の動向に応じて柔軟に対応する必要があり、その難しさが得点として評価されます。 - ゲームのバランス維持
聴牌しているプレイヤーに得点を与えることで、積極的なプレイを促進し、ゲームのバランスを保つ効果があります。全員が防御的なプレイに徹することを防ぎ、ゲームをよりダイナミックに進行させることができます。 - 戦略的な意義
役無しでも聴牌を目指すことで、流局時の点数獲得を狙う戦略が成り立ちます。特に僅差の試合では、役無し聴牌でも点数を積み重ねることで勝利に近づくことができます。
役無し聴牌でも得点を得られるルールは、麻雀の戦略性を高める重要な要素です。これを理解し、状況に応じて適切に活用することで、より効果的なプレイが可能になります。
まとめ
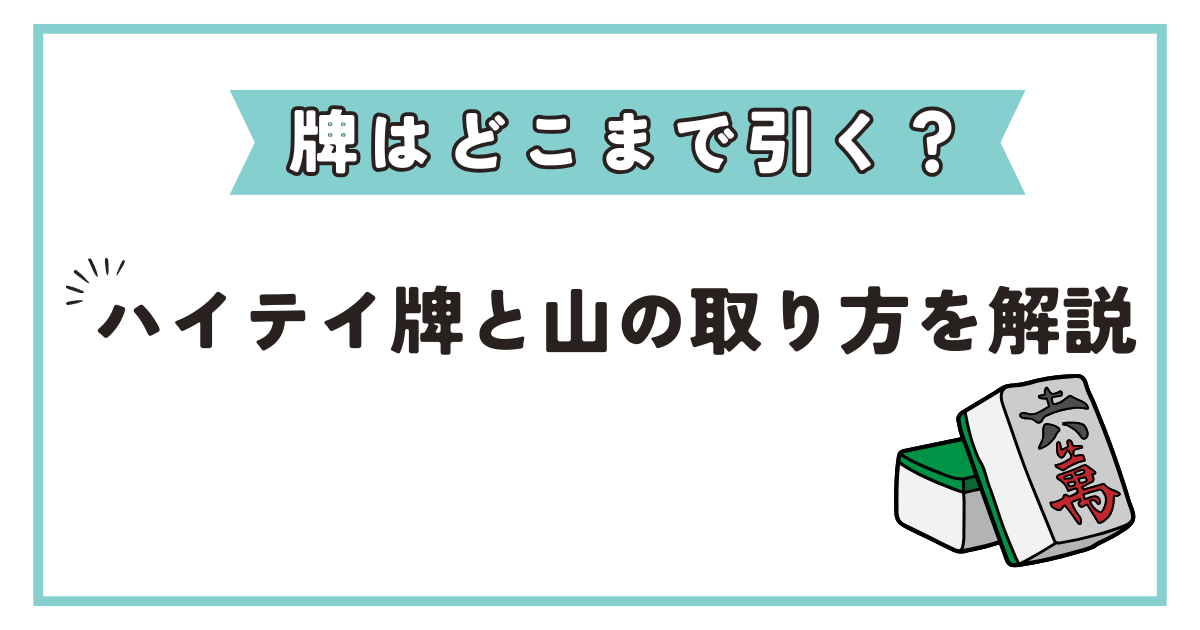
記事のポイントをまとめます。
- 麻雀の一局は誰も和了しなければ流局となる
- 牌山の全てをツモらず、14枚の王牌を残して終了する
- 最後にツモる牌はハイテイ牌と呼ばれ、特別な役が付くことがある
- 王牌にはドラ表示牌やリンシャン牌が含まれ、直接ツモできない
- 流局時に聴牌していればノーテン罰符として点数を得られる
- 親が流局時に聴牌していれば連荘し、聴牌していなければ親流れとなる
- 途中流局は特定の条件下で発生し、九種九牌や四風連打が例として挙げられる
- 途中流局では通常点棒のやり取りは発生せず、局は最初からやり直される
- カンが発生するとツモ回数が増え、王牌からリンシャン牌を引くことになる
- ハイテイ牌はカンの回数によって位置が変わるため注意が必要
- 捨て牌は相手に手牌の情報を与えるため慎重に選ぶ必要がある
- ツモと捨て牌のタイミングは和了の可能性やリスク管理に直結する
- 役無し聴牌でも流局時には点数を得られるため、聴牌維持は重要な戦略
- 供託されたリーチ棒は流局後も次局に持ち越され、アガリ時に回収可能
- 麻雀の進行や流局のルールを理解することで、戦略的なプレイが可能となる